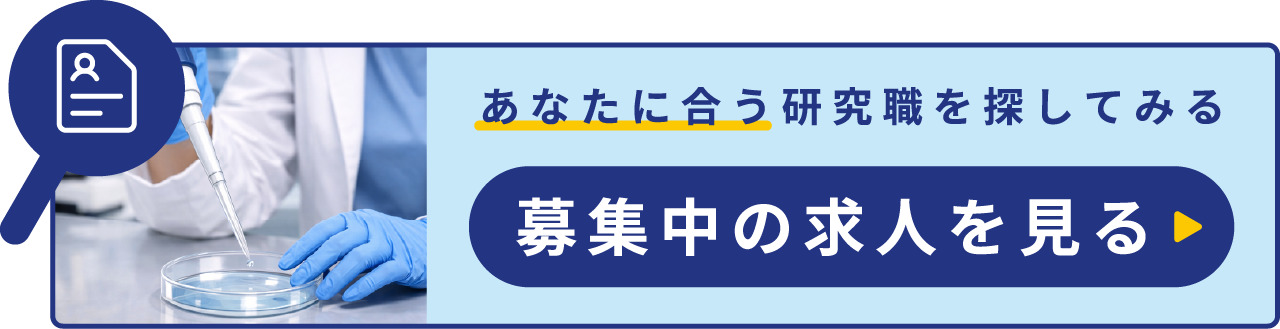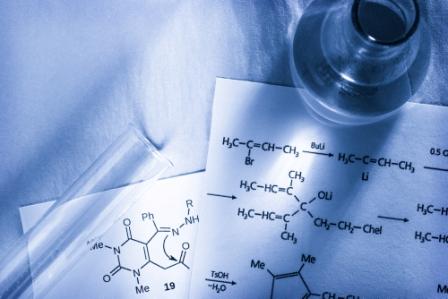バイオ研究者の常識!?PBS溶液の基礎と使い分け
本記事ではPBS/DPBSの定義、基本組成、代表レシピの違い、調製・滅菌・保存、よくあるトラブルまでを整理し、目的に合うPBSの選び方をまとめます。
Contents
バイオ分野の研究に必須アイテムPBS・・・でも瓶にはPBS(-)やD-PBSなどのラベルがある・・・
全部PBSだけどどう違うの!?ポピュラーだけど実はあまりよくわからない。。。
そのお悩みをこのコラムで解決できます!
PBS溶液とは何か
PBS(リン酸緩衝生理食塩水)は洗浄・希釈・懸濁など研究現場で最も頻用される緩衝液の一つです。
一方で「いつも同じ」と思って使うと、pH・浸透圧、Ca2+/Mg2+の有無、メーカー差などが結果に影響することがあります。
PBSの正式名称と役割(緩衝・等張性の維持)を押さえると、なぜ多くの操作で“とりあえずPBS”が選ばれるのかが理解できます。
PBSはPhosphate-Buffered Saline(リン酸緩衝生理食塩水)の略で、リン酸塩でpHを一定に保ちつつ、塩(主にNaClなど)で浸透圧を生理条件に近づけた水溶液です。
研究現場では、細胞や組織、タンパク質などの試料を扱うときに、反応や洗浄の土台として使われます。水だけで洗うと浸透圧差で細胞がダメージを受けたり、pHが動いて分子の状態が変わったりするため、PBSのような「守り」の溶液が必要になります。
ただしPBSは万能ではなく、リン酸が金属イオンと沈殿を作りやすいことや、Ca2+/Mg2+の有無で細胞の挙動が変わることがあります。PBSを単なる消耗品ではなく、条件の一部として意識すると再現性が上がります。
PBSの基本組成とpH・浸透圧
PBSはリン酸塩による緩衝系と、NaCl/KClによる浸透圧調整から成り、配合比がpHやオスモラリティに直結します。
PBSの骨格は、リン酸二水素塩(酸性側)とリン酸一水素塩(塩基性側)の組み合わせによる緩衝系です。両者の比率がpHを決め、総リン酸濃度が緩衝能(pHが動きにくさ)に影響します。
浸透圧は主にNaClとKClなどの無機塩で決まります。浸透圧が低いと細胞が膨潤しやすく、高いと収縮しやすいため、細胞操作では等張付近の範囲にあるかが重要です。メーカー品で浸透圧(例:280~320 mOsm/kg)の規格が示されていることがあるのはこのためです。
PBSはしばしばpH 7.4として扱われますが、実際の規格は製品で幅があり、温度やCO2暴露、保管期間でもわずかに動きます。免疫染色のバックグラウンドやタンパク質の吸着など、微差が効く系では、使っているPBSのpHと浸透圧を一度確認しておくと失敗の切り分けが速くなります。
PBSの代表的なレシピ比較
文献・プロトコル・メーカー品でPBSレシピは微妙に異なるため、何が違い、どこが実験結果に効きうるかを比較の観点で整理します。
PBSは一見どれも同じに見えますが、実際にはNaCl量、KCl量、リン酸塩の種類(Na塩かK塩か)や濃度、pH調整の前提が違うことがあります。こうした差は、イオン強度や緩衝能、タンパク質の溶解性、細胞表面の相互作用に影響し得ます。
重要なのは「PBSかどうか」よりも「そのPBSの組成が何か」です。文献のレシピ、ラボ内の手書きプロトコル、ボトルラベルの成分表が一致しているかを確認し、違う場合はどれを標準にするかを決めておくと、同じ実験でも人や時期で結果が揺れにくくなります。
特に10×ストックから希釈して使う運用では、希釈ミスが起きやすいので、濃度表記(1×/10×)と単位(mM、g/L)の読み違いを減らす工夫が必要です。
NaCl・KCl・リン酸塩濃度の違い
NaClやKClの濃度は、浸透圧だけでなくイオン強度にも影響します。イオン強度が変わると、タンパク質同士やタンパク質と核酸の静電的相互作用が変化し、非特異吸着、凝集、洗浄の効き具合が変わることがあります。
リン酸塩(例:Na2HPO4とNaH2PO4)の比率はpHを、総リン酸濃度は緩衝能を左右します。操作中に酸や塩基が少し混入する系、染色液の希釈でpHがずれると困る系では、リン酸濃度が低いPBSだと想定よりpHが動くことがあります。逆にリン酸が多いほど良いとも限らず、金属イオンと反応して沈殿が出やすくなるなど別のリスクが増えます。
レシピを読む際は、mM(モル濃度)とg/L(質量濃度)を混同しないこと、1×と10×を必ず確認することが基本です。10×をそのまま使うと浸透圧が大きく外れ、細胞や反応系に強いストレスになります。ラベルに最終濃度、希釈方法、作製者と日付を残すだけでも事故は減らせます。
EDTA入りPBSの使いどころ
EDTA入りPBSは、EDTAがCa2+やMg2+などの二価金属イオンをキレートすることで効果を発揮します。代表例は細胞操作で、Ca2+依存の細胞間接着を弱めたり、細胞表面結合をほどきやすくしたりして、洗浄や前処理を安定させる用途があります。
分子生物系では、金属依存のヌクレアーゼ活性を抑える狙いで、DNA/RNAを扱う工程の一時的な懸濁や洗浄に使われることがあります。完全な阻害を保証するものではありませんが、金属イオンを要求する酵素反応の偶発的な進行を抑える補助になります。
一方で不都合も明確です。金属依存酵素(例:一部のプロテアーゼ、リン酸化関連酵素)、金属イオンが必要な結合反応、Ca2+/Mg2+が前提の細胞機能評価では、EDTAが結果を直接変えてしまいます。EDTA入りを選ぶときは「守りたいものは何か」「邪魔してはいけない反応は何か」をセットで考えると判断ミスが減ります。
PBS(+)/PBS(-)の違いと注意点
PBS(+)とPBS(-)は主にCa2+/Mg2+の有無を指し、細胞操作や反応系での“効き方”が変わるため、選択の基準を明確にします。
PBS(+)はCa2+やMg2+を含むタイプ、PBS(-)はそれらを含まないタイプを指すのが一般的です。見た目は同じでも、二価金属イオンは細胞表面分子や酵素に強く関与するため、条件の違いとして効きやすいポイントです。
細胞培養の現場では、洗浄や解離の直前にPBS(-)を選ぶことが多く、これは二価金属イオンがあると接着が強まり、酵素処理やピペッティングでの解離が進みにくくなることがあるためです。逆に、細胞をできるだけ生理条件に近い状態で短時間維持したい、接着を保ちたいなどの意図があるならPBS(+)が有利な場合があります。
注意点として、ボトル表示の「+」「-」が何を意味するかはメーカーによって表記揺れがあり得ます。Ca2+のみ、Mg2+のみ、両方、濃度の違いなどが混在するため、成分表で実際に含まれる塩(CaCl2、MgCl2、MgSO4など)と濃度を確認する運用が安全です。
Ca2+・Mg2+が影響する実験(細胞接着・酵素反応)
Ca2+やMg2+は細胞接着に関わる分子の働きに影響します。例えば細胞間接着の一部はCa2+に依存し、基質への接着や細胞凝集のしやすさも二価金属イオンで変わります。そのため、洗浄のつもりが接着を強めてしまい、回収効率や単細胞化の再現性が落ちることがあります。
細胞解離でトリプシンなどの酵素処理を行う場合、Ca2+/Mg2+があると細胞のまとまりが残りやすく、処理時間が延びたり、強いピペッティングでダメージが増えたりする原因になります。解離工程の直前はPBS(-)を選び、必要ならEDTAの併用や反応停止条件を固定する方が、細胞種間の差を吸収しやすいです。
また、金属依存酵素や金属イオンで結合が変わる反応系では、Ca/Mgの存在が反応速度や結合量を変えます。うまくいかないときは、同じPBSでもCa/Mgの有無を揃えるだけで改善することがあるため、試薬の名前より中身を条件として管理する発想が重要です。
DPBSとは何か
DPBS(Dulbecco’s PBS)はPBSの派生として流通しており、慣習的に“細胞向け”として選ばれることも多いので、PBSとの差分の捉え方を整理します。
DPBSはDulbecco’s phosphate-buffered salineの略で、Dulbeccoが用いた処方に由来するPBSのバリエーションとして流通しています。現場では「細胞用はDPBS」という言い方がされることもありますが、実態としてはDPBSもPBSも複数の処方が存在し、名前だけで厳密な中身を特定できるわけではありません。
DPBSの選択が効くのは、主に細胞操作で求められる品質や仕様が製品として整備されている点です。ろ過滅菌済み、無菌やエンドトキシン、マイコプラズマなどの試験情報が明示される製品が多く、細胞の不調がバッファ由来かどうかを切り分けやすくなります。
結論として、DPBSかPBSかで迷ったら、名称ではなく仕様を見て決めるのが合理的です。pH、浸透圧、Ca/Mgの有無、滅菌方法、試験項目が目的に合っているかを確認すると、同じ「PBS系」でも選定の精度が上がります。
DPBSの組成のメーカー間比較ポイント
DPBSは製品ごとにCa2+/Mg2+の有無、塩の種類(例:MgCl2/MgSO4)、濃度やpH規格、品質試験などが異なるため、比較チェック項目を持つことが重要です。
メーカー間で最も差が出やすいのは、Ca2+/Mg2+の有無と、その供給塩の種類です。MgがMgCl2なのかMgSO4なのか、Caがどの濃度で入っているのかで、イオン環境は同じ「+」表記でも一致しません。特に硫酸塩の有無は、他成分との相互作用や沈殿リスクの評価にも関係します。
次に重要なのがpH規格と浸透圧の範囲です。pH 7.4と書かれていても許容範囲が設定されている場合があり、実験の感度が高い場合にはその幅が無視できません。細胞の洗浄程度なら問題にならなくても、定量染色や結合アッセイでは差として表れることがあります。
細胞培養用途では、無菌、エンドトキシン、マイコプラズマなどの品質試験の有無が実務上の保険になります。トラブル時に原因を切り分けるためにも、購入時にSDSやCoA相当の情報、ロット管理のしやすさまで含めて比較すると、長期的な再現性が上がります。
PBSの作り方(調製・滅菌・保存)
自家調製PBSはコストと柔軟性が魅力ですが、原料・水質・pH調整・滅菌方法・保存条件で再現性が大きく変わります。
自家調製PBSは、目的に合わせてCa/MgなしやEDTA添加などのカスタムができ、コストも抑えられます。一方で、調製者が変わると微差が積み上がりやすく、同じ「PBS」のつもりが実験条件の揺らぎになります。標準手順を作り、測定と記録をセットにすることが再現性の鍵です。
調製では、秤量ミスとpH調整のばらつきが最も起こりがちです。粉末の吸湿、秤の校正、溶解順、最終容量合わせのタイミングがズレると、濃度と浸透圧が意図せず変わります。pHは温度依存があるため、測定温度を決めておくと比較がしやすくなります。
保存は汚染リスクとの戦いです。清潔な分注、使い回しの回避、ラベリング(組成、濃度、pH、作製日、作製者、ロット)を徹底し、異常(濁り、沈殿、pH変動)を早期に検知できる運用にすると、原因不明の失敗が減ります。
原料・水・濃度(1×/10×)の選び方
原料は用途に合うグレードを選びます。分子生物用途、細胞培養用途などで不純物リスクの考え方が違うため、ラボでどの用途を優先するかを決め、同じグレードに統一すると条件ブレが減ります。
水は超純水を基本にし、採水直後の使用や装置のメンテナンス状況も含めて管理します。水が原因の微量金属や有機物は、沈殿や細胞毒性として遅れて表面化することがあり、PBSのトラブルに見えて本質は水質というケースもあります。
濃度は1×作業液と10×ストックを使い分けます。10×は保管スペースや調製頻度を減らせますが、希釈ミスが起きやすいので、希釈手順を固定し、ボトルに最終濃度と希釈方法を明記します。作製日、ロット、pHをラベルに書き、ノートにも残すだけで、後からの検証が可能になります。
フィルター滅菌とオートクレーブの使い分け
フィルター滅菌(一般的に0.22 µmろ過)は、細胞培養での使用や、熱で変化させたくない条件のときに扱いやすい方法です。清潔なボトルと無菌操作が前提で、ろ過前に溶液が完全に溶けていること、フィルターが目詰まりしないことを確認します。
オートクレーブは大量調製に向き、器具込みでまとめて処理できる利点があります。一方で、加熱によりpHがわずかに動いたり、容器由来の溶出や、条件によっては沈殿が出たりすることがあります。オートクレーブ後に外観とpHをチェックし、異常があれば廃棄判断できる運用が重要です。
どちらを選ぶかは、用途の要求水準とスケールで決めます。細胞に直接使う、汚染が許されない、品質試験の代替が必要という場面ではフィルター滅菌が無難です。コストと量を優先しつつ、測定と記録で品質を担保できるならオートクレーブも有効です。
沈殿・pHずれ・汚染のトラブルシューティング
PBSで多いトラブルは沈殿、pHの規格外、微生物汚染であり、原因を切り分けて対策するとロスを減らせます。
沈殿は、リン酸が金属イオンと反応した場合や、濃縮ストックの局所的な高濃度、温度変化による溶解度変化で起きやすくなります。特に10×を作って冷所に置く運用では、成分が偏って沈殿し、上清だけを使うと実質的に組成が変わります。沈殿が出たら再溶解の可否を判断し、再現性が要る実験では作り直す方が安全です。
pHずれは、pHメーターの校正不足、温度差、調製順序、加熱処理、長期保存で起こります。重要なのは、pHを一度合わせたら終わりではなく、どの温度で測ったか、どの方法で合わせたかを手順として固定することです。感度が高いアッセイでは、使用前にpHを点検するだけで原因不明のブレが減ります。
汚染は、ボトルへのピペット先端の接触、複数人での使い回し、キャップの置き方、分注時の無菌操作不足で起きやすいです。濁りが見えた時点で手遅れのことも多いので、分注して小分け運用にし、戻し入れを禁止するのが最も効果的です。細胞用途では、無菌やエンドトキシンの管理レベルが結果を左右し得る点を前提に、購入品と自家調製を使い分けます。
PBS溶液の選び方のまとめ
用途(細胞洗浄、解離、反応バッファ、染色)に対して、pH・浸透圧、Ca/Mgの有無、EDTAの有無、調製形態(1×/10×、粉末/液体)、メーカー仕様をチェックする観点で最終整理します。
PBS選定は、まず用途を言語化するところから始めます。細胞の洗浄や一時懸濁なら等張性と無菌性、解離工程ならCa/MgなしやEDTAの適否、反応バッファや定量染色ならpHとイオン強度の安定性が優先項目です。
次に、仕様をチェックします。pHと浸透圧の規格、Ca2+/Mg2+の有無と濃度、EDTAの有無、滅菌方法(ろ過かオートクレーブか)、品質試験(無菌、エンドトキシン、マイコプラズマ)などを確認し、ラベルやプロトコルに条件として明記します。
最後に運用で再現性を担保します。1×/10×の取り違いを防ぐ表示、作製日とロットの記録、異常(沈殿、濁り、pH変動)の点検を習慣化すると、PBSが原因の失敗は大きく減ります。PBSは脇役ですが、脇役を管理できるラボほどデータの信頼性が上がります。
どうでしたか?PBSについて理解は深まりましたでしょうか。
ワールドインテックではPBSを使うバイオ分野の研究員を募集しております!